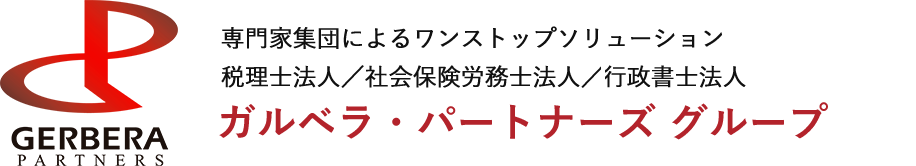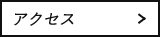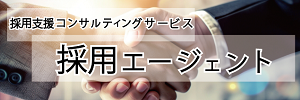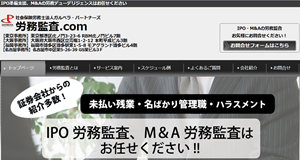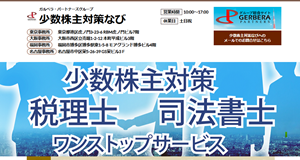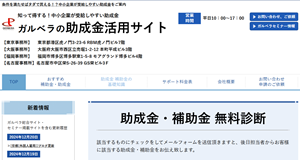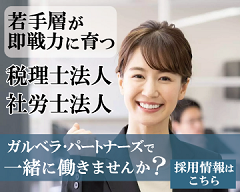生前贈与加算について(見落としがちな点を中心に) | ガルベラ・パートナーズグループ
相続税|生前贈与加算について(見落としがちな点を中心に)
2025/10/07
おすすめ QandA
Q、生前贈与加算について、見落としがちな点について教えてください。

A、遺言やみなし相続財産を受け取った時が失念しがちな点です。以下、詳細に説明します。
解説(公開日:2025/10/07)
生前贈与加算とは、亡くなった方(被相続人)が生前に家族や親しい人へ贈与した財産について、相続の直前一定期間内に受けた場合、その贈与財産を相続財産に「持ち戻して」相続税を計算する仕組みです。これにより、亡くなる直前の「駆け込み贈与」で相続税を回避するのを防ぐことが目的とされています。
この「持ち戻し」の期間は、令和5年度の税制改正で従来の3年から7年へ段階的に延長され、令和6年1月1日以降(2024年以降)の贈与分についてこの新制度が導入されています。つまり、亡くなる前7年以内の贈与までが相続財産に加算される形になります。
生前贈与加算の対象になる人は、主に3つのパターンがあります。
1つ目は「法定相続人」や「代襲相続人」といった相続によって財産を受け取る人。
2つ目は「遺言によって財産をもらう受遺者」。
そして3つ目が「みなし相続財産の受取人」です。
みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金など、民法上の遺産ではありませんが、被相続人の死亡をきっかけに支払われるものを指します。具体的には、保険金の受取人や死亡退職金の受取人が該当し、これらも加算の対象に含まれます。
逆に加算の対象にならない人は、相続放棄をした法定相続人や、法定相続人・受遺者でもみなし相続財産を受け取らない親族(例えば、代襲相続人でない孫や子の配偶者など)などです。また、加算される財産には、暦年課税での年間110万円以下の贈与分も含まれますが、住宅取得や教育資金などの非課税特例枠、配偶者控除枠などは対象外です。
計算上は、贈与時点の財産評価額で持ち戻し、既に贈与税を払っていた場合は、その税額分が相続税から控除されます。また、4年以上前(7年以内)の贈与は100万円控除した額を加算するなど、期間と金額によって取り扱いが異なります。
生前贈与加算の範囲が広がったことで、節税対策を考える際は従来以上に早めの贈与や、法定相続人でない人への贈与、非課税特例のフル活用がより重要になっています。みなし相続財産(特に保険金や退職金)の扱いについては、誤解しやすい部分なので、制度をよく理解した上で贈与や相続の計画を立てることが大切です。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!