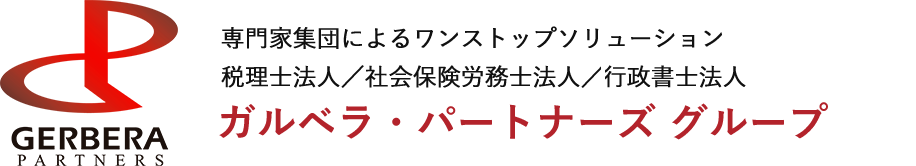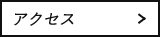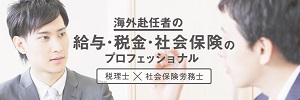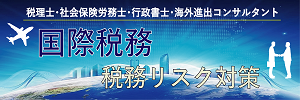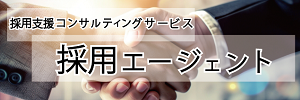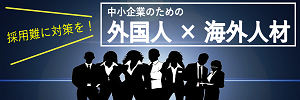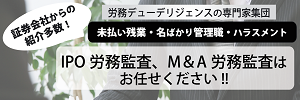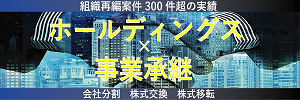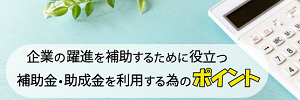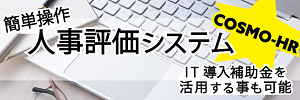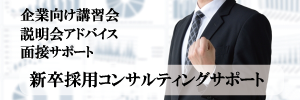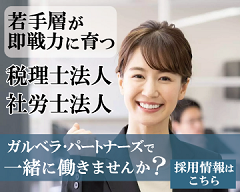法改正情報~メンタルヘルス対策のストレスチェック制度の導入2~ | ガルベラ・パートナーズグループ
メンタルヘルス,ハラスメント対策|法改正情報~メンタルヘルス対策のストレスチェック制度の導入2~
2015/08/25
Q、メンタルヘルス対策として、今年から会社でストレスチェックをしなければならないということですが、これは産業医でないとできないのでしょうか?

A、労働者のメンタルヘルス対策として、2015年12月1日から「ストレスチェック制度」が施行されます。定期健康診断と同様に、「常時使用する労働者50人以上の事業場」が全て対象になりますので、中小企業においては対応に苦慮している事業場も多いかと思います。
解説(公開日: 最終更新日: )
労働安全規則第52条の10において、ストレスチェックの実施者は「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士」とされていますが、こうした医療関係者に依頼できない事業場はどのようにすればよいかという不安が聞かれます。
ただしこの点については、ガイドラインにおいて補足があります。医師や保健師等が、直接ストレスチェックの事務を行わなければならないということではなく、ストレスチェックの実施方法や面接指導の必要性について専門的な見地から意見を述べるという役割が期待されており、調査票の回収・集計・入力等は実施事務従事者に行わせることができるとされています。
(ただし人事部長のように、人事権を有する管理職は直接事務作業を行うことはできませんのでご注意ください。)
以上をまとめますと、ストレスチェック制度の実施体制は次のような役割分担になります。
A) 事業主(または人事労務担当役員など)
ストレスチェック制度の実施について責任を持つとともに、実施方針を策定します。
B) 衛生管理者およびメンタルヘルス担当者等
ストレスチェックの実施について計画立案および実務管理を行います。
C) 実施者(医師、保健師等)
専門的な見地から意見を述べます。
D) 実施事務従事者(従業員や委託業者)
調査票の回収・集計・入力等の事務作業を行います。
また、産業医についても早めに確認が必要です。各事業場の産業医が直接ストレスチェックの実施者となっていただけるようであれば問題はないのですが、様々な事情から、難しい事業場もあろうかと思います。
通達によれば、産業医がストレスチェック及び面接指導等の実施に直接従事することまでを求めているものではなく、衛生委員会に出席して、医学的見地から意見を述べるなど、何らかの形でストレスチェック及び面接指導の実施等に関与することでも差し支えないとされています。
ストレスチェック制度の実施については、まずは自社の産業医に早めに相談してみることをお勧めします。
さて、このストレスチェック制度は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」の57項目を使用して行われることになると思われますが、このような専門的なテストを、自社で集計・分析するのは、技術的に困難と言えます。多くの事業所では、定期健康診断の運営機関などの専門事業者を活用することが多くなろうかと思います。
外部委託に関しては、「ストレスチェック又は面接指導を適切に実施できる体制及び情報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、事前に確認することが望ましい」と通達されています。自社の従業員の大切な個人情報を扱うことになりますので、信頼のおける事業者を選定していただくことが大切かと思います。
最後になりますが、ストレスチェックの実施後の流れについてもご説明いたします。ストレスチェックの結果については、遅滞なく本人に通知され、本人の希望や医師の勧奨により面接指導が実施される場合があります。最後まで責任をもって実施していただくように、注意ください。
- (1)ストレスチェックの実施
- (2)本人に結果通知
- (3)本人から面接指導の申出
- (4)医師による面接指導の実施
- (5)医師からの意見聴取
- (6)事後措置(業務の軽減や配置転換など)
なお、ストレスチェックの実施後は、定期健康診断と同様に、労働基準監督署へ報告が必要です。「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(所定様式)を提出することを忘れないように注意してください。
弊社では、労務問題やコンプライアンス対策のみならず、メンタルヘルス対策や安全衛生管理体制の構築のご相談を承っております。手続や運用も含め、お気軽にご相談ください。
ハラスメント対策 企業内研修のご案内
ガルベラ・パートナーズグループでは、社内のハラスメント意識向上に資する企業内研修をお請けしております。
対象者は全社員または企業幹部限定のいずれかです。
ハラスメント対策研修の特徴
- 1⃣ 社会保険労務士法人による運営ハラスメントによる労務トラブルを数多く見てきた専門家ならではのノウハウを提供します。
- 2⃣ ワークショップによる実体験単なる座学ではなく、ワークショップによる実体験
- 3⃣ ハラスメント規程の作成・改定
ハラスメント対策 企業内研修 180分コース
① ハラスメントとは何かを知る
ハラスメントの状況、ハラスメントの種類、どのようなことがハラスメントになるかを理解する
② ハラスメントが起こった時の企業の責任と当事者の責任
ハラスメントが起こった時に被る影響、責任の重大さ(企業・当事者双方)についての説明
③ ハラスメントが起きた時の対応
ハラスメントが起きる前に企業としてしなければいけないことと実際にハラスメントが起きたときの企業の具体的対応方法を説明
④ 職場からハラスメントをなくす
ハラスメントが起きないようにするための企業の体制等についての説明
| ガルベラセミナー | |
|---|---|
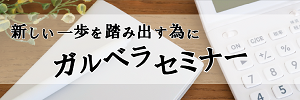 |
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
初回無料相談社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズの業務紹介はこちら
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)

弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!